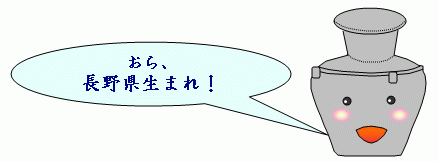トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0046 足原田遺跡
ページID:4518更新日:2025年12月18日
ここから本文です。
遺跡トピックスNo.0046
足原田遺跡〔いしはらだいせき〕
山梨市の遺跡0037足原田遺跡-鞴の羽口-0046足原田遺跡-凸帯付三耳壷-0054延命寺遺跡-台付甕-0221足原田遺跡-食べ物-0296上コブケ遺跡B区-人面装飾付土器-0302上コブケ遺跡C区-発掘調査速報-0313上コブケ遺跡A・B・C区-発掘調査速報-0365上コブケ遺跡B区-県内の人面装飾付土器特集-0346上コブケ遺跡D区-発掘調査速報-0348上コブケ遺跡D区-発掘体験セミナー-0324廻り田遺跡B区-発掘調査速報-0325膳棚遺跡B区-打製石斧-0330膳棚遺跡A区-調査概要-0358膳棚遺跡D区-発掘調査速報-0368膳棚遺跡D区-発掘調査速報2-0373膳棚遺跡D区-遺跡紹介-0384上コブケ遺跡B区-人面装飾付土器の復原修復-0394上コブケ遺跡C区-ナイフ形石器- |
足原田遺跡の詳細は、遺跡トピックスNo.37をご覧ください! 凸帯付三耳壺(とったいつきさんじこ)!?
22号住居跡から、須恵器がバラバラの状態で出土しました。接合作業により、胴部の一番太い部分より少し上に、1条の凸帯と呼ばれる粘土ひもが巡り、この凸帯の上に3箇所の耳のような飾りが付くことがわかりました。口縁部は発見されませんでしたが、胴部の最大径は、約21cm、底部から頸部までの現存する高さは、22.5cm、底部の直径は12.8cmです。耳のような飾りには縦に直径約3ミリの穴が貫通しています。
〔写真〕遺跡の全景(ラジコンヘリコプターで真上より撮影) この壺は、2個残っていた耳のような飾りの位置をみると、もともと耳のような飾りが3つしか付いていなかったのです。長野県の須恵器窯で作られた、この種類の壺は、「凸帯付四耳壺(とったいつきしじこ)」と呼ばれており、耳のような飾りは4つ付いています。山梨県内では、破片で出土することが多く、凸帯と耳状突起が付いているか、また、凸帯部分のみが見つかった場合でも、凸帯付四耳壺と呼ばれていることがあります。足原田遺跡から出土した「凸帯付四耳壺」が、なぜ3つしか耳のような飾りが付いていないのか、担当者は頭を悩ましています。 ちなみに、4つの耳のような飾りを付けることのほうが、3つしか付けないことよりも簡単だと思うのです。丸いケーキを思い浮かべてください。3等分にしようとすると、難しくて、大きさがいろいろになってケンカが起きるかもしれません。しかし、4等分にすることは、それほど難しいことではありません。 長野県で作られたこれらの「凸帯付四耳壺」は、山梨県内では、主に峡北地域で多く発見されています。これは、長野県に近いためだと考えられていますが、甲府盆地東部では、国府や国分寺などに近い遺跡から出土していて、性格の違いを見せているようにも考えられます。足原田遺跡は、盆地東部にあり、国家とのつながりが強い集落のひとつだった可能性が考えられます。
〔写真〕凸帯付三耳壺(とったいつきさんじこ) (左)横から(右)上から赤い円の中が耳のような飾りです。 |