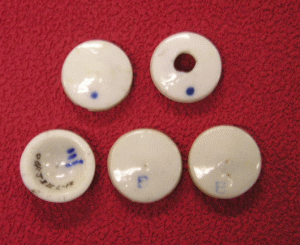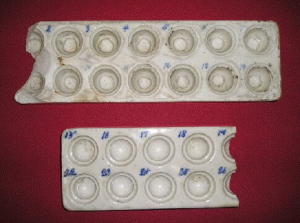トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0116甲府城下町遺跡集緒器
ページID:4567更新日:2025年12月18日
ここから本文です。
遺跡トピックスNo.0116
甲府城下町遺跡 集緒器
甲府城下町の遺跡 |
甲府城下町遺跡は、近世の甲府城を中心として成立した武家屋敷や町人地を含む遺跡です。2005・2006年度の2ヶ年にわたりJR甲府駅北口にある県有地が発掘調査されました。 この地点は甲府城の山手御門に非常に近い場所にあり、幕末の嘉永(かえい)2年(1849年)の『懐宝甲府絵図』第一版(山梨県立図書館蔵)によると嶌田・中島・カモミヤといった勤番士の屋敷や空閑地が広がっていたことが分かります。 その後、大正8年にこのやや北側に製糸工場が建設され翌9年より操業が始まりました。JR甲府駅北口に大きな煙突が残っていたのをご存じの方もあると思います。
JR甲府駅北口県有地調査前の様子
JR甲府駅北口県有地完掘状況(部分)
所在地:甲府市北口二丁目 時代:中世・近世・近代 報告書:山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第258集2009(平成21)年3月刊行 調査機関:山梨県教育委員会山梨県埋蔵文化財センター 出土した製糸関連の遺物集緒器(しゅうちょき)
写真集緒器(しゅうちょき) これは、繭(まゆ)から生糸を作る機械の繰糸機(そうしき)の部品のひとつである集緒器(しゅうちょき)です。中央には直径1mmにも満たない細い穴が開けられており磁器でできていて、ご覧の通り10円硬貨よりも小さなものです。鍋で煮て柔らかくなった繭から糸を繰り出してこの集緒器の細い穴を通って撚りがかけられ糸として巻き取られていきます。また、糸がこの細い穴を通るときに塊となった部分を止める役割も持っています。
写真印のある集緒器 中にはこのように呉須で印をつけて作られた集緒器も見つかっています。繰糸機ごとの区別なのかも知れません。 出土した製糸関連の遺物乳鉢と乳棒
〔写真左〕検査用乳鉢右側面に付けられた商標
ガラス製乳棒 これは、検査用乳鉢とガラス製乳棒です。乳鉢は縦約10cm、横約35cm、厚さ約3cmで磁器でできています。ゴルフボールよりやや窪みが横7カ所に2列開けられており、それぞれの左肩に数字がふられているのが分かります。また、側面には右から左に『実用新案第一三〇六三号』『酒井式検査用乳鉢』『美濃國中津町』と商標が記されています。ガラス製乳棒は長さ4cmほどの大きさをしています。これらで蚕の成虫である蛾(ガ)を乾燥させて磨りつぶして病気がなかったか検査したものだそうです。 生糸は明治から昭和前半では日本の海外輸出の約4割を占めていました。また、大正時代になると欧米でのシルク製ストッキングなどの需要が爆発的に高まり、より高品質な生糸が要求されるようになります。このような検査器具を使って品質を保つことに気を配っていたのでしょう。製糸工業というと長野県や群馬県を思い浮かべますが、山梨県でも生糸生産が盛んに行われ全国的にみても製糸産業の要の一つであったことを忘れてはならないでしょう。 |